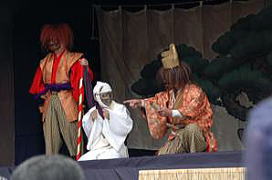|
三田邦彦君
2009/5/30 関西ワンツー会 (京都市北区在住)
 皆様おげんきですか? 小生、半世紀前に小倉を出奔しまして熊本、滋賀、大阪、京都、名古屋と関西エリアを転々として現在、京都市北区紫野雲林院町というところに住んでいます。 皆様おげんきですか? 小生、半世紀前に小倉を出奔しまして熊本、滋賀、大阪、京都、名古屋と関西エリアを転々として現在、京都市北区紫野雲林院町というところに住んでいます。
小倉の学生時代ではまさか京都に住むことになるとは、まったく思いもしませんでしたがこのようなことになりました。会社卒業後のこの地に住み8年経過しましたので、表題のごとく近況と地域のご紹介申し上げますので宜しく。
現在、まだ完全にへその緒きれて仕事は卒業とは行かず、マイペースでごそごそとLED関連のJOBをしています。
住所は「大徳寺」のすぐ近くです。
「大徳寺」は三門の偶像事件で千利休が秀吉からクレームつけられて切腹のトラブルで有名ですが、創始者の「宗峰妙超」、とんち話で有名な「一休宗純」など有名な臨済宗の禅僧を輩出した古刹で織田信長、石田光成、加賀前田家、細川家、お茶の三千家等の塔頭があり、なかなか趣きあります。 「大徳寺」と称しても、京都のどの辺か良くわからない人多いですが、京都の中心から北西の方向で、西陣の北のはしで、近くには「金閣寺」、菅原道真で有名な「北野天満宮」があります。
諸兄は「西陣」の地名由来ご存知ですか?室町時代、応仁の乱の山名宗全率いる西軍の陣地だったことから「西陣」の地名できたそうです。現在は西陣織りも元気ありませんが、都はるみはここの出身です。
 |
 |
| 大徳寺三門 |
紫式部墓所 |
小宅の近くに紫式部のお墓あります。地名が「紫野」ということで紫式部とゆかり深いとのことですが、面白いのは小野篁のお墓と一緒です。小野篁は遣隋史の小野妹子の孫で小野東風、小町など小野一族の名門で、昼は宮中で官僚業務、夜は閻魔大王の執事を勤めたという逸話あり、なかなかの面白い人物のようです。なぜ、紫式部のお墓と一緒かなぞですが、式部が「源氏物語」で男女の仲をあからさまに描いて風紀を乱したという罪で、地獄の閻魔大王の裁きを、小野篁がうまくとりなし無罪にしたことで縁ありという話もあります。写真にもあるように、千本閻魔堂(引接寺)では篁の作ともいわれる閻魔様を祭っています。ここは毎年5月に行われる狂言が面白いです。
 |
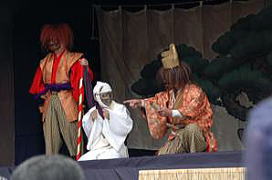 |
| 千本閻魔堂の閻魔様 |
閻魔堂で行われる狂言 |
また近くには安部清明を祭っている清明神社、小生、茶はやりませんが、裏千家茶室「今日庵」、表千家「不審庵」も近くです。「陰陽師」に描かれている平安時代のイメ-ジがあちこちに残っています。京都は毎月何かお祭りやっています。三大祭りで5月の葵祭り、7月の祇園祭り、10月の時代祭りが有名ですが歴史から言うと、葵祭りがもっとも古く、上、下賀茂神社の祭事です。祇園祭りは小倉の祇園太鼓でもなじみですが八坂神社のお祭りですが、ここはスケールが大きく、雅の要素多く迫力満点です。時代祭りは、明治以降の産物で京都御苑から平安神宮(明治時代に建立)まで仮装行列です。明治維新のピーヒャラの軍楽隊が先頭で各時代の風俗衣装が見ものです。また、8月には有名な五山の送り火(大文字焼き)でお盆を終了します。小宅は北区なので、「舟形」がよく見えます。
いろいろ京都のPRになりましたが、老人にとっては神社仏閣多く、行事もたくさんあり結構楽しめます。
 |
 |
| 葵祭り「競べ馬」 |
葵祭り「花車」 |
 |
 |
| 時代祭り「巴御前」 |
祇園祭り「山鉾巡行」 |
金閣にも近いので、雪降った朝は雪解けない内に写真撮影にゆきます。「雪の金閣」はなかなかきれいでした。
小宅近場の寺社仏閣の紹介になりましたが、あちこちチャリンコで訪問、いろいろ面白く気楽に送っています。ゴルフは下手ですが100切るように、月一程度で頑張っています。
 |
 |
| 雪の金閣 |
五山の送り火「舟形」 |
12期ワンツー-会関西地区では、松尾幹事のもと大阪で会合持って参りましたが、今春、京都哲学の道の桜見物にウォーキング゙で汗流しました。 皆さん年の割にはとても元気で脱落者なしでした。皆様、是非京都へ遊びに来てください。
 |
| 左から松尾・安永・吉村・岡田(古賀)・前田(木畑)・松尾夫人・三田の各位 |
|



 皆様おげんきですか? 小生、半世紀前に小倉を出奔しまして熊本、滋賀、大阪、京都、名古屋と関西エリアを転々として現在、京都市北区紫野雲林院町というところに住んでいます。
皆様おげんきですか? 小生、半世紀前に小倉を出奔しまして熊本、滋賀、大阪、京都、名古屋と関西エリアを転々として現在、京都市北区紫野雲林院町というところに住んでいます。