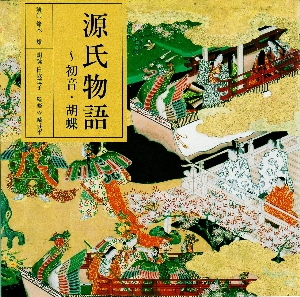“平安王朝文学と貴族の恋愛―女流日記と源氏物語を通してー (その4)
もとに宮仕えすることになる。これまでと違う環境と立場に置かれて知った苦労、その中で見聞きしたこと、成長する姿などは「紫式部日記」からつぶさにうかがえる。やがて紫式部は、優秀な女房として貴族に認められ、中宮彰子の信頼や同僚の人望も得るほどの存在になってゆく。
時代が一条天皇の世から三条天皇、そして彰子の息子の後一条天皇(敦成親王)の時代へと動いても、紫式部は彰子の傍らに寄り添い、彼女を支え続けた。1008年11月1日敦成親王誕生50日のお祝いの席で左衛門の督藤原公任が「あなかしこ、このわたりに若紫はさぶろう(失礼。この辺りに若紫さんはお控えかな)」。
彼は紫式部を探して呼びかけているが、その際彼女を「若紫」と「源氏物語」の女主人公の名で呼びかけた。現在伝わる「源氏物語」関係資料で、年月日まで明記してある中では最も日付の古い資料である(2008年11月1日は源氏物語千年紀)。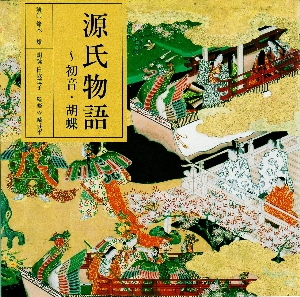
「源氏物語」について、西暦1008年に少なくとも若紫登場部分は存在したこと。それが女性読者ばかりでなく藤原公任のような男性の公卿に読まれるほど広まっていたことが知られる。室町時代の系図集「尊卑文脈」には、紫式部について「御堂関白道長妾云々」という注記が付けられている。その真偽は不明である。が、宮仕えという場が女房にとっても男性にとっても色事の起りやすい環境であったことは確かである。紫式部とてもたとえある夜は拒んだとしても後日には受け入れたかもしれない。高貴な男性と浮名を流すことは女房にとって決して不名誉ではなく、むしろ誇れることであった。まして紫式部は既に夫もおらず、道長の思い人になることには何の支障もない。一方の高貴な男性にとっても、艶福家の姿を文芸作品に書きとめられるのが一つの誉れであったことは、先の道長の父兼家が登場する「蜻蛉日記」などからも推測できる。紫式部の心情として「源氏物語」の帚木・空蝉の巻で、「源氏がある晩、方違えに中川の紀伊守の邸へ行き、紀伊守の父の若い後妻、空蝉に逢い、無理に犯す。源氏がはじめて知った中流のこの女は、思いがけない自尊心を見せ、手厳しい抵抗をみせる。しかし心のうちでは、ああ、こんな風に受領の妻という身分が決まってしまった境遇ではなく、亡くなった両親の思い出の生家にいて、たまさかにでも、源氏の君のお通い下さるのをお待ち申し上げるのだったなら、どんなに楽しいことだろうに。せっかくのお気持ちを強いて感じないふりを装ってはいるものの、どんなにか身の程知らぬ女とお思いになられるだろうと、自分で決心したことなのに、さすがに胸がねじれそうに痛く、あれこれと思い乱れてしまうのでした。けれども、今はどうしようもない自分の宿世なのだから、あくまで情のきつい、いやな女のままで押し通そうと、覚悟を決めたのでした」とある。
「源氏物語」に描かれた密通―源氏物語には、近代人からすれば「不義・不倫」と非難されるべき男女の関係が数多く描かれている。この物語最初の先の空蝉の話のような身分の低い女との関係はともかくとして、源氏は天皇の女御であり、自分の父の妻でもある藤壺に近づいて子を儲け、さらにその子は皇位に昇るという大事件が書かれている。
またその一方で源氏は、皇太子で異母兄の朱雀院と結婚直前の朧月夜に近づいて、その結婚を中止させている。この源氏と朧月夜との関係は、やがて朧月夜が内侍として入内してからも続き、朱雀院はそれを知ってからも特に咎めてはいない。若菜の巻では、柏木は源氏の妻女三宮に近づいて薫を生ませている。
宇治十帖に入っても、匂宮は、幼いころからの親友である薫の妻浮舟に通じている。この物語では、そうした「不倫」とすべき男女の関係が多く描かれているだけではなくて、むしろそれこそがこの物語の書こうとした重要な主題になってもいるのである。源氏物語を読んでいて不思議に思うのは、それらの「不倫」をなした当事者たち、源氏や藤壺や朧月夜などのいずれもが、自己のその「不倫」についてうしろめたさをおぼえたり、自分は「不義」「不倫」をなした、との意識がまったくないように見えることである。
空蝉が、源氏に強く抵抗し拒んだのは、こんな形で源氏を受け入れては自分がみじめ過ぎる、というもっぱら自己の誇りのためであり、決して自分は人妻だからと考えてのことではなかった。
なお下記の書物を参考にさせて頂いた。
「蜻蛉日記」−川村裕子(p296~299) 「更級日記」−原岡文子(p224~230)
「和泉式部日記」−近藤みゆき(p224~225) 「紫式部日記」−山本淳子(p246~248)
「枕草子」−坂口由美子(p105~106,167) (以上 角川ソフィア文庫)
「平安貴族の結婚・愛情・性愛」−増田繁夫(p57〜60,186~187)(青簡舎)
「源氏物語」 −瀬戸内寂聴訳」(巻1-p102) (講談社)
―完―
杉本善昭
その5を読む
|